後継者におススメの書籍
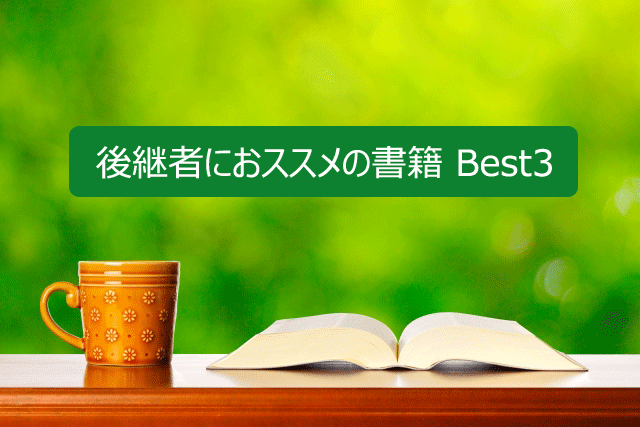
生き方 稲盛和夫著
京セラとKDDIを創業し、JALを再生に導いた「経営のカリスマ」と呼ばれている稲盛和夫さんの著書です。
経営者として、人としての生き方を勉強することができる内容で、どの部分も素晴らしく、一部分を引用することは難しいのですが、後継者に参考になる部分のみ書きます。
本著では、京セラが発展した理由として、次のように書かれています。
嘘をついてはいけない、人に迷惑をかけてはいけない、正直であれ、欲張ってはならない、自分のことばかりを考えてはならないなど、だれもが子どものころ、親や先生から教わった――そして大人になるにつれて忘れてしまう――単純な規範を、そのまま経営の指針に据え、守るべき判断基準としたのです。
昨今の経営においては、コンプライアンスが重視され、対策専門部署でコンプライアンス違反にならないための努力が必要になりましたが、上記の経営指針に従ってさえいれば、そんな労力は必要がないということです。
また、「労働」に関しては次のように述べられています。
一般によく見受けられる考え方は、労働とは生活するための糧、報酬を得るための手段であり、なるべく労働時間は短く給料は多くをもらい、あとは自分の趣味や余暇に生きる。それが豊かな人生だというものです。そのような人生観をもっている人のなかには、労働をあたかも必要悪のように訴える人もいます。 しかし働くということは人間にとって、もっと深遠かつ崇高で、大きな価値と意味をもった行為です。労働には、欲望に打ち勝ち、心を磨き、人間性をつくっていくという効果がある。単に生きる糧を得るという目的だけではなく、そのような副次的な機能があるのです。
🙋♂️私の意見
ワークライフバランスという言葉が一般的になり、労働はほどほどにして、生活をエンジョイすることが大切だとされていますが、私も以前から、労働で得られる喜びは他のものには代え難いと感じています。特に後継者には、一心不乱に仕事をしなければ成功はないと考えています。もちろん後継者にも家庭を大切にしていただきたいですが、ワークとライフを分けるのではなく、そもそも「ワークはライフに含まれる」と考えた方が良いと思います。
上記の稲盛さんの文章を読み、そんなことを考えました。
何回読み返していただいても良い内容なので、是非ご一読ください。
町工場の娘 主婦から社長になった2代目の10年戦争 諏訪 貴子著
創業者である父親が急逝し、主婦であった次女が一念発起して町工場の後継者になったものの、バブル崩壊後の不景気の影響下、赤字経営で苦労し、そこから経営を復活させたストーリーです。
先代からの引継ぎがない状態で、経営状況も悪かったため、銀行や取引先の協力も得られずに、孤軍奮闘されている後継者のリアルな状況が描かれています。
🙋♂️私の意見
この本を読むと、「事業承継対策は何よりも早期の準備が必要」と痛感させられます。
先代からの事業承継が進まないとお感じの後継者は、本書の内容を「事業承継対策に取り組まなかった場合の悪事例」として研究されることをお勧めします。
チームのことだけ、考えた。――サイボウズはどのようにして「100人100通り」の働き方ができる会社になったか 青野 慶久著
本書は、グループウエアで有名な「サイボウズ」という会社の創業期から発展していく中で、多様性のある組織づくりを実施する際の試行錯誤が描かれています。
昨今では、どの企業も人材確保が重要になっており、多様性のある人事制度づくりは、参考になる点が多いと思います。
ただ、後継者に是非読んでいただきたいのは、多様化前、創業メンバーが悪戦苦闘して会社を成長させていった部分です。
創業メンバーは、文字通り「死ぬ気で働いていた」様子を表す言葉として、本文中に次のような言葉があります。
-
週6日で給料ゼロ過労死寸前まで働く
-
止まると死ぬ止まらなくても死ぬ
-
頑張るのと命をかけるのではレベルが違う
🙋♂️私の意見
後継者は先代の経営に不満を抱くことがあるかもしれませんが、今、引き継ぐ会社が存在するということは、先代が死に物狂いで会社を興して発展させたということです。まず、先代の様々なチャレンジを苦労されたことを知っていただき、その上で、「命をかけて」後継者になるということを、あらためて考えていただければと思います。




